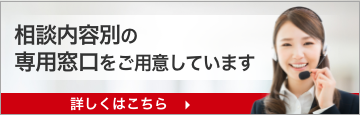年俸制なら就業規則で「退職は3か月前の申し出を必須」と規定できるか
- 労働問題
- 就業規則
- 退職
- 3ヶ月前

埼玉県のホームページによると、令和4年度に寄せられた労働相談は5223件あり、内、退職についての相談は428件あったことが報告されています。県や市区町村が実施する労働相談は、労働者はもちろんのこと、使用者側も利用できますが、全体の47.3%が正規労働者、非正規労働者は全体の36.3%を占めています。
企業としては、人材不足は経営に大きくかかわる問題です。もし従業員から辞めたいと告げられても、すぐに辞めてもらっては困ると考えるかもしれません。では、代わりの人材を見つける時間を確保するために、退職する際は3か月前までに予告するよう就業規則を定めることは可能なのでしょうか。ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスの弁護士が解説します。
1、就業規則は事業所が定める独自のルール
就業規則とは、給与規定や労働条件、職場内の規律やルールなどをまとめた規則のことをいいます。各会社によって、独自にさまざまな決まりがあります。そのため、「退職する場合は3か月前までに予告しなければならない」旨を定めることができそうに思えるかもしれません。
実際に、さまざまな会社で、このような退職前の予告期間が定められています。このような規則は有効になるのでしょうか。
-
(1)法的な退職予告期間のルール
就業規則は、正社員のほか、働いてもらうすべての人に適用される会社独自のルールです。そのため、すべての規定について労働者の同意が必要だと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。場合によっては、会社が労働条件を定めること自体は可能になっています。
しかしながら一方で、労働者は、労働基準法などの労働法によって保護されています。したがって、労働基準法などの規定に反する就業規則は、たとえ会社が定めたとしても、結局無効になってしまう場合があるのです。
それでは、法律上、退職前の予告期間についてはどのように定められているのでしょうか。まず、期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条の存在を無視することはできません。
民法第627条1項においては、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と規定されています。この規定によると、期間を定めていない労働者の場合は、2週間前に退職を予告すれば、退職が認められてしまうことになるのです。たとえ就業規則によって、退職届は3か月前に出すことを定めていたとしても、このような法律を無視することはできません。
つまり、退職の予告期間を就業規則で定めていたとしても、労働者側が、法律の規定に従って退職の予告をした場合、会社側が退職を引き留めることはできないケースがあるのです。
-
(2)年俸制では「3か月前」は有効にできるのか?
期間の定めがない従業員が退職の意向を出せば、いくら就業規則で「3か月前」に申し出る旨を定めていたとしても、法律上は2週間で退職できてしまうことは前述のとおりです。
企業としては、せめて月給制や年俸制を導入している従業員に対しては、民法第627条の2項と3項に定められている以下の規定を根拠に、就業規則を定めたいと考えるかもしれません。
民法第627条
2項「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」
3項「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」
しかし、これらの規定は使用者、つまりは雇用する企業側が従業員を解雇したり契約終了を申し渡したりするケースについて定められたものです。したがって、期限の定めがない労働契約を結んでいる従業員自身が自主退職の申し出をする場合、法律上は2週間前までに申し出れば企業側は退職を認めなければならないことを知っておきましょう。
なお、期間の定めのある労働契約を結んだ従業員が契約期間途中に退職を申し出た場合は「やむを得ない事由」があれば、企業側は退職を認めなければなりません。しかし、「やむを得ない事由」がない場合であっても、会社側が退職を認めるのであれば、退職することに問題はないでしょう。もっとも、1年を経過したのちはいつでも自由に退職することができます(労働基準法137条)。
どのように就業規則を定めたらよいのか等の疑問点については、弁護士からアドバイスを受けることが可能です。就業規則についてお悩みの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
2、定める予告期間に遅れて退職届が出された場合は?
就業規則で定められている退職予告期間に遅れて退職届が提出された場合、会社はどのように対処すればよいのでしょうか。
-
(1)退職を認めなければならない場合
期間の定めのない労働契約の場合、前述のとおり、法律上は、退職の予告から2週間で退職が成立するものとされています。したがって、退職の予告から2週間が経過している場合、会社は退職を認めざるを得ないでしょう。
なお、解雇の場合は、30日前の解雇予告義務や解雇予告手当を支払わなければならないという決まりがあります。しかし、労働者による一方的な解約である退職にはこのような規制はありません。すなわち、就業規則で定めている退職予告期間に遅れて退職の予告をして辞めたからという理由だけで、当然に、退職した社員に対して金銭の支払いを求めることはできません。 -
(2)退職を認めなくてもよい場合
他方、法律で定めている退職予告期間にすら遅れて退職届が出された場合には、当該退職日での退職を認めなくても法的には問題ないでしょう。
3、退職届を受理しなかった場合に起こりうるリスク
期間の定めのない労働契約の場合、たとえ予告期間を3か月と就業規則で定めていたとしても、社員から退職の申し出があった場合、2週間で退職が成立してしまうことになるでしょう。もちろん、その社員が考え直した上で、改めて退職日を会社と社員間で調整し、円満な退職となるのは、社員にとっても会社にとってもメリットがあるはずです。
しかし、大きな戦力となっている労働者からの退職届については、受理せずに当該労働者にもう少し働いてもらいたいと思う場合もあるでしょう。では実際に、会社側が退職届を受理せず、結果的に在職を強要した場合どうなるのか、起こりうるリスクをご説明します。
まず、退職届を会社側が受理しなかったとしても、法律で定められている以上、退職の申し出から2週間以上たてば、退職は成立するでしょう。
さらに労働者は、自分の権利を守ってもらうために、労働基準監督署に相談することができます。結果、労働基準監督署からの調査や指導があった場合、会社は大きな不利益を受ける可能性があるでしょう。
このように、就業規則で社員の退職を縛ることはできませんし、会社側からの命令で退職ができないようにするということもできません。また、辞めるからといって支払うべき給料支払いを拒否することもできません。
退職届が提出された場合、受理する必要があります。しかし、退職を予告される前に何らかの対策をしたいとお考えであれば、弁護士に相談することをおすすめします。会社ができる権利や被るリスクなどについて具体的な指摘とアドバイスができるでしょう。
4、まとめ
会社は労働者と雇用契約を結ぶことにより、一定の労働力を提供してもらうことができます。もちろんその労働力に対して賃金を支払うことで、一定の関係が保てることとなるのです。
他方、会社としては、せっかく戦力として育てた人材の流出は大きな損失となるため、できる限り退職してもらいたくないと考えることは当然です。さらに、人手不足により、事業が継続できなくなるおそれもあるため、できる限り、人手不足にならないよう就業規則で退職予告期間を長めに設定したいと思うかもしれません。
しかし、就業規則よりも法律の規定が優先されることは多いことから、就業規則は絶対ではありません。人材流出などを就業規則で対策したいと検討しているときや、実際に従業員とトラブルになってしまった場合は、ベリーベスト法律事務所 大宮オフィスまでお気軽にご相談ください。担当の弁護士が状況に適したアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています